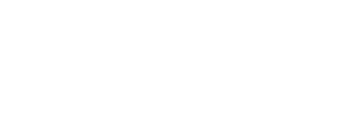元箱根から望む富士山と箱根神社の鳥居
【駿府城公園】
静岡市葵区にある徳川家康公ゆかりの城跡。家康公が大御所として晩年を過ごした駿府城の遺構で、東御門・巽櫓、坤櫓は寛永年間再建時に近い姿で再現されている。
12月初旬。ひんやりとした夜気が残る早朝に自宅を発ち、徳川家康ゆかりの静岡へと向かった。温暖な気候に恵まれた静岡は、古より豊かな自然環境を継承し、今川氏や家康の城下町として独自に発展を続けてきた。今回は数々の歴史舞台となった駿府城跡を訪ね歩く。
JR静岡駅に降り立つ頃には、すっかり陽射しは高くなっていた。雲ひとつない穏やかな晴天。少し歩いただけで汗ばむ陽気は本当に師走なのだろうか。出発前に、念のためにともう一枚重ね着したことを後悔する。
JR静岡駅から北へ徒歩15分程歩いたところで、その姿は見えてきた。1996年に復元された東御門から園内に入ると、昼休み中の近隣の官庁勤めの人たちや、外国人観光客らがゆったりとした時間を過ごしていた。周辺には高い建物がなく、四方を見渡すと、どこまでも爽やかな青空が続く。
家康没後の寛永12年(1635)、城下の出火で飛び火したことにより、駿府城は天守と御殿を焼失した。いまや当時の面影を伺い知れる建物は、復元された巽櫓と二ノ丸東御門など一部のみとなるが、園内からは富士山を一望でき、家康がこの場所を誇ったのも頷ける。

「徳川家康公之像(駿府城本丸後)」
鷹狩りに出かけた際の晩年の姿を表している。高さ6.5m(像高3.5m)の銅像。昭和48年建立。
家康は人生で3度、駿府に居した。最初は岡崎城主の身分のまま8歳で今川家の人質として送られてきた幼年期、次に豊臣秀吉の命により赴いた壮年期、最後は将軍職から退いた大御所時代の晩年期だ。慶長10年(1605)、息子の秀忠に将軍職を譲った家康は、駿府城を幕府の迎賓館として機能させ、各国諸大名や外国使節団を迎え入れた。もうひとつ駿府に拠点を移した理由に、西の豊臣勢を牽制する目的があったともいわれている。
広い園内の北西側には天守台発掘現場がある。ここで出現した慶長期と天正期のふたつの天守台は、どちらも家康が築かせたとみられていた。しかし、後の天正期天守台からは、秀吉の大坂城に相当する高い技術力や豪奢な特徴がみられたのだ。秀吉政権下で確立された画期的な築造技術の使用は、秀吉の側近にしか許されていなかったこと、また当時の家康にはそこまでの力がなかったことなどから、駿府城は家康の意思ではなく、相模の北条討伐を狙いとする秀吉の命だったという見解となった。
東を威嚇する目的で築かれた城は、秀吉没後、西を威嚇する要衝となったのだから皮肉なものだ。政治の舞台となるファクターが揃い、ふたりの天下人が睨みを効かせた駿府。もしタイムスリップができるなら、この天下分け目の時代を鳥瞰してみたい。

「富士見芝生広場から望む富士山」
空気が澄んだ快晴の日には、広場から雄大な富士山を一望できるビュースポット。

「静岡市のカラーマンホール蓋」
久能山東照宮と駿河湾、一富士・二鷹・三茄子を織り込んだデザイン。市役所周辺に限定10個設置。
駿府城公園に隣接する県庁横に、博物館があると聞き立ち寄った。2023年1月にオープンした静岡市歴史博物館では、駿府に大きな功績を残した家康の一生を中心に、今川家や静岡の歴史について展開。当時の城下町の賑わいや人々の暮らしぶりも公開されている。
特筆すべきは「戦国時代末期の道と石垣の遺構」をそのまま展示してある1階スペース。家康も歩いたかもしれないその道の長さは30m、両側に武家屋敷があったと推定される。全国的にみてもとても貴重なギャラリーは一見の価値あり。駿府城公園とのセット見学をオススメしたい。
歴史を知ることは自分を知ることでもある。先祖や自分に縁がないと思われる地域や歴史上の人物も、遡れば必ずどこかで交差し地続きで繋がっているものだ。旅には転地効果があるといわれる。そこに「歴史」というアクセントを加えることで、より人生が多彩になるのではと感じている。

「静岡市歴史博物館」
2023年1月にグランドオープン。歴史探求と体験、交流を融合した新スタイルの博物館。
【施設情報】
〒420-0853 静岡市葵区追手町4-16
(開館時間)9:00-18:00(定休日)月曜、年末年始
※祝日の場合は月曜開館、翌平日休館

「戦国時代末期の道と石垣の遺構」
発掘調査で見つかった、東西に伸びる道とその両脇の石垣。静岡市歴史博物館の1階エリアで無料見学ができる。

「駿府城跡天守台発掘調査現場」
常時観覧できる「見学ゾーン」と調査に関する情報を展示している「発掘情報館きゃっしる」を併設。
「駿府城公園」
園内には家康手植えのミカンなどが残存。4つの庭で構成された日本庭園と茶室を備えた紅葉山庭園など、四季折々の花を楽しめる。

「巽櫓」
全国にある櫓建築でも例の少ないL字型の平面をもつ。駿府城の櫓の中では防御機能に優れた櫓だったといわれる。

「東御門」
駿府城二ノ丸の東に位置する主要出入口。現在の建物は、寛永年間再建時の姿を目指して平成8年(1996)に復元された。